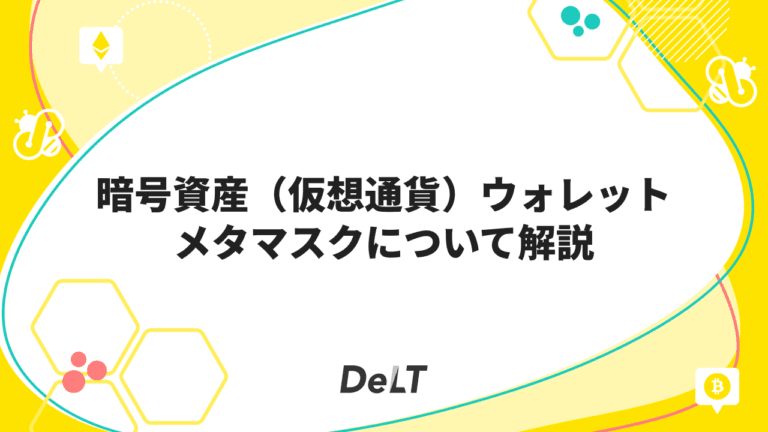【RISC-V とは?】ブロックチェーンへの応用について分かりやすく解説
2025/04/22

「RISC-V」という言葉を聞いたことがありますか?最近、ブロックチェーン界隈で注目を集めているRISC-Vは、コンピュータの「頭脳」であるプロセッサの設計図に関するものです。そして今、イーサリアム(Ethereum)の創設メンバーであるプログラマー、ヴィタリック・ブテリン氏がこのRISC-Vを活用してイーサリアムを劇的に進化させる大胆な提案を行い、世界中の暗号資産コミュニティが沸き立っています。
本記事では、ブロックチェーンやコンピュータ技術に詳しくない方でも理解できるよう、RISC-Vとは何か、なぜブロックチェーンとの相性が良いのか、そしてどのような未来を切り開く可能性があるのかを解説します。
記事の目次
RISC-V とは?コンピュータの「頭脳」を自由に設計できる革命的技術
皆さんが日々使っているスマートフォンやパソコン、さらには家電製品や自動車などに搭載されているコンピュータには、必ず「プロセッサ」と呼ばれる頭脳が存在します。このプロセッサがどのように動作するかを決める設計図が「命令セットアーキテクチャ(ISA)」と呼ばれるものです。RISC-V(リスク・ファイブ)は、完全に無料で自由に利用できるオープンソースの命令セットアーキテクチャです。
従来のプロセッサ設計図は、IntelやARM(スマートフォンに多く使われている)といった特定の企業が所有し、利用するには高額なライセンス料を支払う必要がありました。しかしRISC-Vは誰でも無料で使え、自由に改変できるため、特定の用途に最適化したカスタムプロセッサを低コストで開発できる革命的な技術なのです。
RISC-Vは「Reduced Instruction Set Computer(縮小命令セットコンピュータ)」の第5世代という意味で、シンプルな命令セットを採用することで高効率な処理を実現しています。スマートフォンのバッテリー持ちを良くしたい、AIの計算を高速化したい、またはブロックチェーン処理に特化したいなど、様々な目的に応じて最適な「頭脳」を設計できるのがRISC-Vの大きな魅力です。
オープンソースの力で急速な進化
RISC-Vは、2010年にカリフォルニア大学バークレー校でKrste Asanović(クルステ・アサノビッチ)教授と大学院生たちが始めた研究プロジェクトから誕生しました。当初は「短い3ヶ月の夏季プロジェクト」として始まったRISC-Vですが、学術研究と産業界の両方で利用できるオープンソースのコンピュータシステムを作るという理念のもと開発されました。
2015年には「RISC-V財団」に管理が移管され、その後「RISC-V International」という国際的な非営利団体として発展しました。現在、RISC-V Internationalはスイスに本部を置き、政府規制に左右されない中立性を維持しながら、世界中の設計者のためにこの標準を管理しています。
RISC-Vが誕生してから急速に広がった背景には、オープンソースの力があります。オープンソースとは、ソフトウェアやハードウェアの設計図を公開し、誰でも自由に利用・改変・再配布できるようにする開発モデルです。Linuxオペレーティングシステムやインターネットの基盤技術の多くがオープンソースで成功したように、RISC-Vもオープンソースの利点を活かし、世界中の開発者や企業が協力して改良を重ねることで急速な進化を遂げています。
2022年末までに、RISC-Vを搭載したチップは100億個以上出荷されたと報告されており、その採用は今も拡大し続けています。特に中国や新興国では、外国企業への技術依存からの脱却を目指して積極的にRISC-V技術の採用が進んでいます。
自由でカスタマイズ可能な仕組み
RISC-Vの最大の特徴は、そのモジュール性と拡張性にあります。RISC-Vは基本となる小さな命令セット(ベースISA)と、目的に応じて追加できる拡張機能から成り立っています。これは積み木のように、必要な機能だけを組み合わせてプロセッサを設計できることを意味します。
例えば、小型のIoTデバイス(モノのインターネット)であれば最小限の命令セットだけを使い、人工知能の処理が必要なら特別な計算用の拡張を追加するといった具合です。必要な機能だけを選んでカスタマイズできるため、用途に最適な性能、消費電力、サイズ(PPA: Performance, Power, Area)を実現できます。
RISC-Vアーキテクチャは以下のような優れた設計特性を持っています:
- シンプルな命令体系: 複雑な命令を避け、シンプルな基本命令を効率的に実行する設計
- 固定長の32ビット命令: 処理をシンプルかつ高速に
- モジュラー設計: 基本命令セットに拡張機能を追加可能
- スケーラビリティ: 小型デバイスからスーパーコンピュータまで幅広いアプリケーションに対応
- アーキテクチャ的に中立: 特定のマイクロアーキテクチャや実装方法に依存しない
従来のプロセッサ設計では、IntelやARMなどの特定企業の命令セットを使わざるを得ず、ライセンス料や設計の制約がありました。しかしRISC-Vでは、ユーザーが自由に設計を改変でき、ロイヤリティも発生しません。
これは特にブロックチェーン技術との相性が良く、暗号処理に特化した命令セット拡張や、ゼロ知識証明(ZKP)の処理を効率化する拡張など、ブロックチェーン特有の処理に最適化したプロセッサを誰でも設計できる可能性を開きました。そのため近年、ブロックチェーン分野でRISC-Vへの注目が高まっているのです。
ブロックチェーンとRISC-Vはなぜ相性が良いのか?
ブロックチェーン技術とRISC-Vは一見、まったく異なる分野の技術に思えますが、両者の組み合わせは多くの相乗効果を生み出す可能性を秘めています。ブロックチェーンは取引記録や契約を安全に保存・実行するための分散型台帳技術ですが、処理速度やエネルギー効率、セキュリティといった課題を抱えています。RISC-Vはこれらの課題に対する解決策となり得るのです。
ブロックチェーンの処理には、暗号計算や合意形成アルゴリズムなど、特殊な計算処理が必要です。従来のIntelやARMのプロセッサは汎用的に設計されているため、これらの特殊処理には必ずしも最適ではありません。RISC-Vならブロックチェーン特有の処理に最適化したカスタムプロセッサを設計できるため、処理効率の大幅な向上が期待できます。
また、ブロックチェーン技術の普及には、IoT(モノのインターネット)デバイスとの統合が重要な鍵となっています。2030年までに200億以上のデバイスがIoTネットワークに接続されると予測されていますが、これらの多くは電力供給に制限があります。RISC-Vは省電力設計が可能なため、バッテリー駆動のIoTデバイスでもブロックチェーン処理を効率的に行えるようになるでしょう。
2021年、RISC-V International内に「ブロックチェーンSIG(特別利益グループ)」が設立されました。このグループはRISC-Vアーキテクチャとブロックチェーン技術の統合を促進し、プライバシー保護や暗号アルゴリズム、信頼実行環境などの分野で業界標準を超える性能とセキュリティを実現することを目指しています。この取り組みにより、RISC-Vとブロックチェーンのエコシステムは急速に発展しています。
ブロックチェーン応用 – 高効率と高セキュリティの実現
ブロックチェーンが直面している最大の課題の一つが処理効率です。イーサリアムなどの主要ブロックチェーンは、処理速度の制限から一秒あたりの取引数(TPS)が限られており、これが大規模採用の障壁となっています。RISC-Vプロセッサはブロックチェーン向けに特化した暗号計算ユニットを実装できるため、ハッシュ関数や電子署名などの処理を大幅に高速化できます。
例えば、研究者たちは「SHA3」(ブロックチェーンで広く使われるハッシュアルゴリズム)の計算に特化したRISC-V拡張を開発しています。この拡張を使用すると、SHA3の処理が通常のプロセッサと比較して数倍から数十倍高速化される可能性があります。これにより、ブロックチェーンの処理性能が劇的に向上し、より多くの取引を処理できるようになります。
セキュリティ面では、RISC-Vは以下のような利点を提供します:
- ハードウェアレベルの暗号化サポート: RISC-Vプロセッサに暗号拡張機能を実装することで、暗号化処理を高速かつ安全に実行
- オープンソースによる透明性: コードが公開されているため、セキュリティの脆弱性を発見しやすく修正も迅速
- カスタマイズ可能なセキュリティ機能: 用途に応じた最適なセキュリティ機能を実装可能
- 信頼実行環境(TEE): センシティブなデータや処理を保護する特別な実行環境を構築可能
特に注目すべきは、RISC-V上に構築された「zkVM(ゼロ知識仮想マシン)」で、これはプライバシーを保護しながらブロックチェーン取引を検証できる革新的な技術です。ゼロ知識証明(ZKP)は、データの中身を公開せずにその正当性を証明する暗号技術ですが、計算負荷が高いという課題がありました。RISC-V zkVMはこの処理を効率化し、プライバシー保護と処理効率を両立させます。
エネルギー効率も重要なポイントです。ビットコインのマイニング(採掘)が大量の電力を消費することは広く知られていますが、RISC-Vベースのカスタムプロセッサを使用することで、ブロックチェーン処理のエネルギー消費を大幅に削減できる可能性があります。研究によれば、ブロックチェーン処理用に最適化されたRISC-Vプロセッサは、従来のプロセッサと比較して最大で70%のエネルギー削減が可能との結果も出ています。
このように、RISC-Vとブロックチェーンの組み合わせは、処理効率、セキュリティ、エネルギー効率の面で大きな改善をもたらします。これにより、ブロックチェーン技術の実用性と普及が加速することが期待されています。
ヴィタリック・ブテリン氏による提案と背景
2025年4月20日、イーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏が、暗号資産コミュニティを驚かせる大胆な提案を行いました。イーサリアムのコア技術であるEVM(イーサリアム仮想マシン)をRISC-Vアーキテクチャに置き換えるという提案です。この提案が実現すれば、イーサリアムの処理効率が最大で100倍も向上する可能性があるとブテリン氏は述べています。
現在、イーサリアムは取引処理速度やガス(手数料)の高さが課題となっており、ユーザー数の増加とともにネットワークの混雑が深刻化しています。また、より高速な競合ブロックチェーン(SolanaやSuiなど)の台頭により、イーサリアムの市場シェアも脅かされつつあります。RISC-Vへの移行は、イーサリアムがこれらの課題を解決し、次世代ブロックチェーンとして進化するための「唯一の実行可能な道」とブテリン氏は考えているようです。
この提案はイーサリアムの次回アップグレード「Pectra」(2025年5月7日予定)の直前に発表されたものであり、その大胆さと技術的な合理性から、多くの開発者やイーサリアムコミュニティから注目を集めています。
EVMからRISC-Vへの移行が何を意味するのか
イーサリアムの中核には「EVM(イーサリアム仮想マシン)」と呼ばれる仮想コンピュータが存在します。これはイーサリアム上でスマートコントラクト(自動実行される契約プログラム)を実行するための環境です。現在のEVMは独自の命令セット(バイトコード)を使用していますが、ブテリン氏の提案ではこれをRISC-Vアーキテクチャに置き換えようとしています。
この変更の中核にあるのは、効率性の問題です。現在、イーサリアムのスケーリングに使われている「ZK(ゼロ知識)証明」技術は、EVMコードをRISC-Vアーキテクチャに変換してからシミュレーションする必要があります。これは非常に非効率なプロセスです。RISC-Vを直接採用することで、この変換プロセスを省略でき、大幅な効率向上が見込めます。
具体的には、以下のような変更が提案されています:
- 開発者がSolidityなどの言語を直接RISC-Vにコンパイルできるようにする
- SLOADやCALLなどのシステム操作をオペコードではなくシステムコールとして処理する
- 既存のEVMコントラクトとRISC-Vベースの新しいコントラクトが共存できる仕組みを構築する
重要なのは、この変更が「裏側」でのみ行われ、開発者は引き続きSolidityなどの慣れ親しんだ言語を使ってスマートコントラクトを書くことができる点です。ツールチェーンが内部でRISC-Vに適応するため、開発者は大きな変更を行う必要がありません。
RISC-V 採用で変わるイーサリアムの未来
RISC-Vアーキテクチャの採用がイーサリアムにもたらす可能性のある変化は計り知れません。最も直接的な効果は処理効率の向上で、場合によっては100倍もの高速化が期待できます。これにより、現在イーサリアム上で実行するには高すぎる複雑な計算や大量のデータ処理が可能になります。
具体的なメリットとしては以下が挙げられます:
- トランザクション処理速度の劇的な向上: より多くの取引を処理できるようになり、ネットワーク混雑が緩和される
- ガス(手数料)コストの削減: 処理効率が向上することで、各操作に必要なガス代が減少
- 新しいアプリケーションの可能性: 現在は計算コストが高すぎて実装できなかった複雑なアプリケーションが実現可能に
- ゼロ知識証明の効率化: プライバシー保護技術やスケーリングソリューションがより効率的に
しかし、この提案には課題もあります。実行レイヤーの完全な再設計は膨大な作業を伴い、最低でも数年の開発期間と莫大なリソースが必要になるでしょう。また、既存のスマートコントラクトを新システムにどのように移行するかという問題も残されています。
イーサリアム財団の新共同エグゼクティブであるTomasz K. Stańczakは、ブテリン氏の提案は「有望な道筋を進めた」と評価しつつも、これはあくまで議論を始めるためのものであり、コミュニティがさらに洗練させたり、別の形に発展させたりする可能性があると述べています。
RISC-Vへの移行は、イーサリアムが単なる「スマートコントラクトプラットフォーム」から真の「世界コンピュータ」へと進化するための重要なステップとなるかもしれません。この提案が実現すれば、イーサリアムは次世代ブロックチェーンとの競争力を維持しつつ、より多くのユースケースをサポートできるようになるでしょう。ブロックチェーン技術の未来にRISC-Vが重要な役割を果たすことは間違いなさそうです。
ブロックチェーンでの実用例
RISC-Vとブロックチェーンの融合は単なる理論上の話ではなく、すでに多くの実用プロジェクトが進行しています。世界中の企業や研究機関がRISC-Vを活用したブロックチェーンソリューションの開発に取り組んでおり、革新的な成果が次々と生まれています。これらのプロジェクトは、ブロックチェーン技術の課題であった処理効率、セキュリティ、エネルギー消費の問題に対して、RISC-Vの特性を活かした解決策を提供しています。
例えば、RISC-V International内の「ブロックチェーンSIG」には、万向ブロックチェーン、aitos.io、LeapFive、SiFive、StarFiveなどの主要企業が参加しています。これらの企業は協力して、RISC-Vアーキテクチャ上でブロックチェーン技術を効率的に実行するための標準やツールを開発しています。
特に注目すべきは、RISC-V向けに最適化された暗号拡張機能の開発です。ブリストル大学暗号グループが手がけるXCryptoプロジェクトなどでは、RISC-V向けの暗号アルゴリズム実装を高速化・効率化する拡張セットが開発されています。これらの拡張は、ブロックチェーンの基盤となる暗号処理を大幅に高速化し、エネルギー効率を向上させることが期待されています。
また、Casperブロックチェーンはすでにゼロ知識証明(ZKP)技術と組み合わせたRISC-V実装を採用しており、プライバシー保護と計算効率の両立に成功しています。このようなプロジェクトは、RISC-Vがブロックチェーンの実用性を高める上で大きな役割を果たせることを実証しており、業界の注目を集めています。
zkVMでの活用例
RISC-V技術を活用したブロックチェーン分野の最も革新的な開発の一つが「zkVM(ゼロ知識仮想マシン)」です。zkVMはゼロ知識証明(ZKP)技術とRISC-Vアーキテクチャを組み合わせた仮想マシンで、データのプライバシーを保護しながら計算の正確性を証明できる画期的なシステムです。
中でも注目すべきは「RISC Zero」プロジェクトです。RISC Zeroは、zk-STARK技術とRISC-Vマイクロアーキテクチャに基づくゼロ知識検証可能な汎用コンピューティングプラットフォームを開発しています。RISC Zeroの革新的な点は、任意のプログラミング言語(主にRust、C、C++)で書かれたコードをRISC-V向けにコンパイルし、その実行を暗号学的に証明できる点です。
RISC Zero zkVMの仕組みは以下のようになります:
- 証明したいコードをRISC-V対応のELFファイル(実行可能ファイル)にコンパイル
- zkVM内でそのコードを実行し、実行の記録を作成
- 暗号学的な証明(ゼロ知識証明)を生成
- 他のユーザーはその証明を検証することで、データの中身を知ることなく実行の正確性を確認できる
この技術がブロックチェーンにもたらす革新性は計り知れません。zkVMを活用することで、ユーザーはプライバシーを保護しながら複雑な取引や計算を行い、その結果の正確性を第三者に証明できるようになります。例えば、個人情報を含む金融取引や、機密性の高いビジネスロジックを公開せずに実行できるようになるのです。
RISC Zero zkVMはすでに複数のブロックチェーンと統合されており、クロスチェーン(異なるブロックチェーン間)でのゼロ知識証明の検証を可能にする「ユニバーサルベリファイア」も開発されています。これにより、チェーンをまたいだシームレスな証明検証が実現し、ブロックチェーン間の相互運用性が大幅に向上します。
さらに、RISC Zeroは形式検証(フォーマルベリフィケーション)を活用して、zkVMの安全性と正確性を数学的に証明する取り組みも行っています。これにより、RISC-V zkVMは非常に高速でありながらも証明可能に安全なシステムとなり、ブロックチェーンアプリケーションの信頼性向上に貢献しています。
IoTブロックチェーンでの活用例
IoT(モノのインターネット)とブロックチェーンの組み合わせは長年注目されてきましたが、その実現にはエネルギー効率やセキュリティなどの課題がありました。RISC-Vはこれらの課題を解決し、IoTデバイスとブロックチェーンの統合を加速させる鍵となっています。
特に注目すべきは、「メモリスタベースのイン・メモリ・コンピューティング(IMC)」を採用したRISC-Vプロセッサの開発です。この技術は、ブロックチェーンでよく使われるKeccakハッシュアルゴリズムなどの処理を大幅に効率化します。従来のIoTデバイスではリソース制限から実装が困難だった複雑なハッシュアルゴリズムが、RISC-Vベースのカスタムプロセッサによって低消費電力で実現できるようになりました。
実際の応用例として、aitos.ioが開発したIoTデバイス向けの「BoATブロックチェーンアプリケーションフレームワーク」があります。このフレームワークはRISC-Vプラットフォーム向けに最適化されており、小型のIoTデバイスでもブロックチェーンサービスに参加できるようにしています。これにより、センサーデータの信頼性確保や、デバイス間の自律的な取引などが可能になります。
RISC-VとIoTブロックチェーンの統合がもたらす具体的なメリットには以下があります:
- 電力効率の大幅な向上: バッテリー駆動デバイスでも長時間動作可能
- カスタマイズ性: 特定のブロックチェーン機能に最適化されたハードウェア
- セキュリティ強化: ハードウェアレベルの暗号化サポートによる高いセキュリティ
- コスト削減: オープンソースアーキテクチャによる開発・製造コストの低減
これらの特性により、スマートシティ、サプライチェーン管理、産業用IoT、スマートグリッドなど、多様な分野でRISC-Vを活用したIoTブロックチェーンの実用化が進んでいます。例えば、工場内のセンサーが収集したデータをRISC-Vプロセッサで処理し、ブロックチェーンに記録することで、製造プロセスの透明性と信頼性を向上させる取り組みが始まっています。
2030年までには、RISC-Vを搭載したIoTデバイスとブロックチェーンが融合した「分散型コグニティブ産業インターネット」や「デジタルシティ」といった構想が実現に近づくと期待されています。これにより、私たちの日常生活や産業のあり方が大きく変わる可能性があります。
RISC-V とブロックチェーンが創る未来
RISC-Vとブロックチェーンの融合は、単なる技術的なイノベーションを超え、社会のあり方自体を変える可能性を秘めています。この2つの技術の組み合わせは、より分散化され、高効率で、プライバシーが保護された次世代のデジタルインフラを実現する基盤となるでしょう。現在すでに様々な実験的プロジェクトが進行していますが、今後5〜10年の間に、私たちの生活や社会システムに大きな変革をもたらすことが予想されます。
特に注目すべきは、RISC-Vがブロックチェーン技術の民主化を加速させる可能性です。RISC-Vのオープンソース性により、大企業だけでなく、スタートアップや個人開発者、さらには発展途上国の組織でも、高性能なブロックチェーンインフラの構築が可能になります。これはインターネットの普及が情報アクセスを民主化したように、ブロックチェーン技術の恩恵をより広い層に届ける役割を果たすでしょう。
また、RISC-Vの柔軟性は、ブロックチェーン技術の応用範囲を大幅に拡大します。従来は処理能力やエネルギー消費の制約から実現できなかった複雑なブロックチェーンアプリケーションが、RISC-Vの採用により現実のものとなる可能性があります。これは金融サービスだけでなく、ヘルスケア、エネルギー管理、都市計画など、私たちの生活に関わる様々な分野に革新をもたらすでしょう。
ブロックチェーンへの活用の課題と展望
RISC-Vとブロックチェーンの統合には大きな可能性がある一方で、克服すべき課題も存在します。最大の課題の一つは、この新しい技術の標準化と互換性の確保です。現在、様々なプロジェクトが独自のアプローチでRISC-Vとブロックチェーンの統合を進めていますが、これらが異なる標準を採用すると、将来的な相互運用性に問題が生じる可能性があります。
RISC-V International内の「ブロックチェーンSIG」などの団体は、この問題に対処するために標準化作業を進めていますが、業界全体での合意形成はまだ途上にあります。特に、暗号アルゴリズムの実装やゼロ知識証明の標準プロトコルなど、セキュリティに関わる重要な部分での標準化が急務です。
もう一つの課題は、ソフトウェア開発ツールとエコシステムの成熟度です。RISC-Vは比較的新しいアーキテクチャであるため、従来のIntelやARMプラットフォームと比較すると、開発ツールやライブラリの充実度にまだ差があります。ブロックチェーン開発者がRISC-Vプラットフォームを効果的に活用するためには、より直感的で強力な開発環境が必要です。
また、再現可能なビルドの実現も重要な課題です。ZKVMなどのシステムでは、コンパイラの選択やバージョン、コンパイル環境などによって異なる結果が生じる可能性があり、これはブロックチェーンのセキュリティや検証において問題となりえます。一部のプロジェクトではDockerコンテナ内でRISC-Vバイナリを生成するなどの対策を講じていますが、より根本的な解決策が求められています。
これらの課題にもかかわらず、RISC-Vブロックチェーンの展望は明るいものです。特に注目すべきは、形式検証(フォーマルベリフィケーション)の分野での進展です。RISC-Vの単純な設計思想は数学的な検証に適しており、ブロックチェーンのセキュリティ向上に大きく貢献する可能性があります。Ethereum財団も形式検証されたRISC-V ZKVMの開発に取り組み始めており、これが実現すれば、ブロックチェーンの信頼性は飛躍的に向上するでしょう。
今後数年間で、RISC-Vとブロックチェーンの統合は加速し、エネルギー効率の向上、プライバシー保護技術の進化、スケーラビリティの改善といった成果が見込まれます。これにより、ブロックチェーン技術は現在の実験的段階から、より広範な社会実装の段階へと進化していくでしょう。
私たちの生活はどう変わるか
RISC-Vとブロックチェーンの融合は、一般の人々の日常生活にどのような変化をもたらすのでしょうか。最も直接的な影響は、金融サービスの変革でしょう。RISC-Vによって高速化されたブロックチェーンは、より使いやすく低コストな金融サービスを実現します。
例えば、現在の国際送金は高額な手数料と数日間の処理時間を要することがありますが、RISC-Vで最適化されたブロックチェーンでは、わずか数秒で世界中どこへでも送金が完了し、手数料も大幅に削減される可能性があります。また、マイクロペイメント(少額決済)が実用的になることで、記事1つの閲覧やストリーミング1分間など、より細かい単位でのデジタルコンテンツの購入が可能になるでしょう。
もう一つの大きな変化は、デジタルアイデンティティの革新です。RISC-V zkVMを活用したプライバシー保護型のアイデンティティシステムにより、ユーザーは自分の個人情報を完全にコントロールしながら、必要な情報だけを安全に証明できるようになります。例えば、年齢確認の際に生年月日全体ではなく「20歳以上である」という事実だけを証明するといったことが可能になります。
サプライチェーン管理においても大きな変革が起きるでしょう。RISC-Vを搭載したIoTデバイスからの情報をブロックチェーンに記録することで、製品の原材料調達から消費者の手元に届くまでの全プロセスを透明化できます。食品の産地や製造過程、医薬品の品質管理など、消費者にとって重要な情報が簡単に確認できるようになります。
「マシン・ツー・マシン経済(M2M経済)」の出現も期待されます。RISC-Vを搭載した自律型デバイスがブロックチェーン上で直接取引を行い、人間の介入なしにサービスや資源を交換する経済システムが生まれる可能性があります。例えば、自動運転車が充電ステーションから電力を購入したり、データセンターがコンピューティングリソースを取引したりするような世界です。
このように、RISC-Vとブロックチェーンの融合は、私たちの生活のあらゆる側面に変革をもたらす可能性を秘めています。しかし、これらの変化が社会に受け入れられるためには、技術的な課題の解決だけでなく、社会制度や規制の整備、そして何より一般ユーザーにとっての使いやすさの向上が不可欠です。RISC-Vブロックチェーンの真の成功は、高度な技術が日常生活に溶け込み、私たちがその存在を意識することなくその恩恵を享受できるようになったときに達成されるでしょう。
参考:
https://cointelegraph.com/news/vitalik-buterin-proposes-swapping-evm-language-risc-v
https://www.cryptotimes.io/2025/04/20/vitalik-buterin-proposes-risc-v-to-replace-ethereums-evm/
https://cset.georgetown.edu/article/risc-v-what-it-is-and-why-it-matters/
https://vac.dev/rlog/zkVM-explorations/
注意事項
- 本記事は、情報提供のみを目的としており、投資助言や金融商品の売買を推奨するものではありません。
- 本記事では、正確な情報提供に努めておりますが、その完全性、正確性、適時性、有用性等について、保証いたしかねます。
- 本記事に記載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
- 暗号資産(仮想通貨)への投資判断は、ご自身の責任において行ってください。投資を行う際は、取引所の利用規約および取引に関する説明事項をよく読み、リスクについて十分に理解した上で、ご自身の判断と責任において行ってください。
- 本記事の内容は、予告なく変更または削除される場合があります。