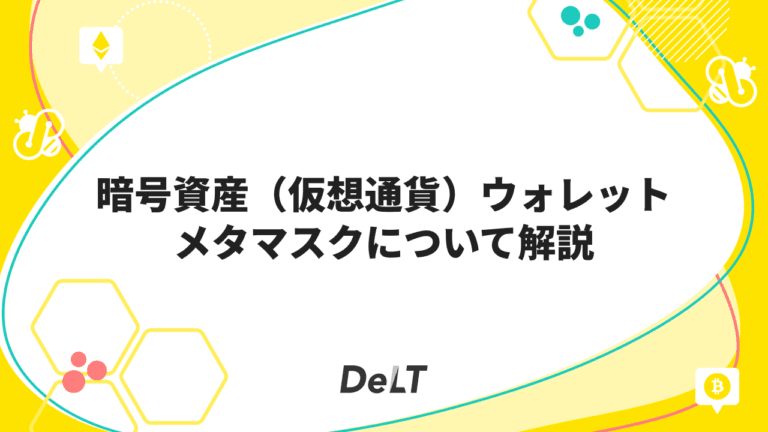AMMとは?暗号資産(仮想通貨)の自動マーマットメイカーを解説
2025/09/03

AMM(自動マーケットメイカー)は、暗号資産(仮想通貨)の取引に革命をもたらした仕組みです。
従来の取引所が注文板(オーダーブック)で売買をマッチングさせるのに対し、AMMは流動性プールとスマートコントラクトを活用して、自動的に価格を決定し取引を実行します。UniswapやPancakeSwapなどのDEX(分散型取引所)で採用されているAMMの仕組みは、24時間いつでも取引可能で、誰でも流動性提供者として参加できる点が大きな特徴です。
本記事では、AMMの基本的な仕組みから、代表的なプロトコル、流動性提供によるリスクと報酬、そして初心者が安全に始める方法まで、包括的に解説していきます。DeFiの中核を担うAMMを理解することで、暗号資産運用の新たな可能性が見えてくるでしょう。
記事の目次
AMMの基本的な仕組みとは?従来の取引所との違いを解説
AMMとは、Automated Market Makerの略称で、日本語では「自動マーケットメイカー」と呼ばれています。AMMは、ブロックチェーン上で動作するスマートコントラクトによって、暗号資産の売買を自動化する革新的な仕組みです。
従来のCEX(中央集権型取引所)では、オーダーブック方式と呼ばれる仕組みが採用されています。オーダーブック方式では、売りたい人と買いたい人の注文を板(オーダーブック)に並べ、価格が一致したときに取引が成立します。例えば、「1ETHを50万円で売りたい」という売り注文と「1ETHを50万円で買いたい」という買い注文がマッチングすることで取引が実行されます。
一方、AMMでは、流動性プールと呼ばれる資産の貯蔵庫を相手に取引を行います。流動性プールには、あらかじめ2種類以上のトークンが預けられており、ユーザーは流動性プールに自分のトークンを入れて、代わりに別のトークンを受け取る形で取引を実行します。価格は数式によって自動的に決定されるため、取引相手を探す必要がありません。
自動マーケットメイカーによる24時間取引の実現
AMMの最大の特徴は、スマートコントラクトによる完全自動化された取引システムです。スマートコントラクトは、あらかじめプログラムされたルールに従って自動的に実行されるプログラムで、人間の介入を必要としません。AMMにおけるスマートコントラクトは、流動性プールの管理、価格計算、取引の実行をすべて自動で処理します。
ブロックチェーンは24時間365日稼働し続けるため、AMMを利用した取引もいつでも実行可能です。従来の取引所のようにメンテナンス時間や営業時間の制約がなく、世界中のどこからでもアクセスできます。また、取引の約定も即座に行われるため、注文が約定するまで待つ必要がありません。流動性プールに十分な資産があれば、どんな時間帯でも確実に取引を完了できる点が、AMMの大きなメリットです。

さらに、AMMでは取引の透明性が確保されています。すべての取引はブロックチェーン上に記録され、誰でも確認できます。スマートコントラクトのコードも公開されているため、どのような仕組みで価格が決定され、取引が実行されるのかを確認することが可能です。
流動性プールと価格決定の数式(x*y=k)
AMMの価格決定メカニズムの中核となるのが、流動性プールと数式による価格計算です。最も広く採用されている価格決定方式は、「x*y=k」という定数積フォーミュラ(Constant Product Formula)です。Uniswap V2やPancakeSwapなど、多くのAMMプロトコルがこの数式を基本としています。
流動性プールには、例えばETHとUSDCのように、2種類のトークンがペアで預けられています。x*y=kの式において、xはプール内の一方のトークン(例:ETH)の総量、yはもう一方のトークン(例:USDC)の総量、kは定数を表します。取引が行われても、xとyの積は常に一定(k)に保たれるように価格が自動調整されます。
具体例を挙げて説明すると、ETH/USDCプールに10ETHと10,000USDCが預けられていて、k=100,000だとします。ユーザーが1ETHをプールに入れてUSDCを受け取る場合、プール内のETHは11ETHに増加します。kを一定に保つため、USDC量は100,000÷11≈9,091USDCとなり、ユーザーは約909USDC(10,000-9,091)を受け取ることになります。

この仕組みにより、大量の取引が行われるほど価格への影響(プライスインパクト)が大きくなります。流動性プールが大きければ大きいほど、個々の取引による価格変動は小さくなり、より安定した取引が可能になります。
DEXにおけるAMMの重要性と役割
AMMは、DeFi(分散型金融)エコシステムにおいて極めて重要な役割を果たしています。DEX(分散型取引所)の多くがAMMを採用している理由は、パーミッションレスな環境で効率的に流動性を提供できるためです。
従来のオーダーブック方式では、十分な流動性を確保するために多数の市場参加者が必要でした。特に新しいトークンや小規模なプロジェクトでは、買い手と売り手を見つけることが困難で、流動性が不足しがちでした。AMMの登場により、少ない参加者でも流動性プールを作成し、取引を可能にすることができるようになりました。
AMMのパーミッションレスな設計により、誰でも新しいトークンペアの流動性プールを作成できます。プロジェクト開発者は、中央集権型取引所の厳しい上場審査を経ることなく、自由にトークンを流通させることが可能です。この特性により、イノベーションが加速し、多様なDeFiプロジェクトが生まれる土壌となっています。
また、AMMはDeFiプロトコル間の相互運用性を高める役割も果たしています。レンディングプロトコル、イールドアグリゲーター、デリバティブプラットフォームなど、様々なDeFiサービスがAMMの流動性を活用して機能しています。AMMは単なる取引の場ではなく、DeFiエコシステム全体の基盤インフラストラクチャーとして機能しているのです。
流動性提供者(LP)のメリットとリスクを理解する
AMMが機能するためには、流動性提供者(LP:Liquidity Provider)の存在が不可欠です。流動性提供者は、自身の暗号資産を流動性プールに預けることで、取引の円滑化に貢献し、その見返りとして報酬を受け取ります。

しかし、流動性提供には特有のリスクも存在するため、メリットとリスクの両面を理解することが重要です。流動性提供者になるには、まず対象となる流動性プールに等価値の2種類のトークンを預ける必要があります。例えば、ETH/USDCプールに流動性を提供する場合、1,000ドル分のETHと1,000ドル分のUSDCを同時に預け入れます。預け入れと引き換えに、LPトークンと呼ばれる流動性提供の証明となるトークンを受け取ります。LPトークンは、プール内での自分の持ち分を表し、資産を引き出す際に必要となります。
手数料報酬とガバナンストークンの仕組み
流動性提供者の主な収入源は、取引手数料報酬です。AMMでは、トレーダーが取引を行うたびに一定の手数料(多くの場合0.3%程度)が徴収されます。徴収された手数料は、流動性提供者の間でプール内の持ち分に応じて分配されます。
例えば、Uniswap V2では0.3%の取引手数料のうち、0.25%が流動性提供者に分配され、0.05%がプロトコルの準備金として積み立てられます。取引量が多いプールほど手数料収入も増加するため、人気のあるトークンペアの流動性提供は高い収益性が期待できます。年間利回り(APR)が10%を超えるプールも珍しくありません。
多くのAMMプロトコルでは、手数料報酬に加えてガバナンストークンも報酬として配布されています。ガバナンストークンは、プロトコルの運営方針を決定する投票権を持つトークンです。UniswapのUNI、Curve FinanceのCRV、PancakeSwapのCAKEなどが代表的なガバナンストークンです。
ガバナンストークンの配布は、「流動性マイニング」や「イールドファーミング」と呼ばれる仕組みを通じて行われます。特定のプールに流動性を提供したり、LPトークンをステーキングしたりすることで、追加報酬としてガバナンストークンを獲得できます。ガバナンストークン自体にも市場価値があるため、売却して利益を得ることも、保有してプロトコルの意思決定に参加することも可能です。
インパーマネントロス(変動損失)への対策方法
流動性提供における最大のリスクは、インパーマネントロス(Impermanent Loss)と呼ばれる変動損失です。インパーマネントロスは、流動性プールに預けたトークンの価格比率が変動することで発生する潜在的な損失を指します。
具体的に説明すると、ETHとUSDCを1:1000の比率でプールに預けた後、ETHの価格が2倍に上昇したとします。プール内では自動的にリバランスが行われ、ETHが売却されUSDCが購入されます。結果として、流動性提供者が保有するETHの量は減少し、USDCの量は増加します。もしETHを単独で保有していれば価格上昇の恩恵を100%受けられたのに対し、プールに預けていたことで利益が減少してしまうのです。
インパーマネントロスを軽減する対策として、以下の方法があります:
- ステーブルコインペアの選択:USDC/USDTなど、価格変動が少ないペアを選ぶことでリスクを最小化
- 相関性の高いペアの選択:ETH/stETHなど、価格が連動しやすいトークンペアを選択
- 手数料収入との比較:高い取引量があるプールでは、手数料収入がインパーマネントロスを上回る可能性
- 短期的な流動性提供:価格変動が大きくなる前に資産を引き出す戦略
インパーマネントロスは「一時的な」損失と呼ばれる理由は、価格比率が元に戻れば損失も解消されるためです。しかし、実際には価格が完全に元に戻ることは稀であり、慎重なリスク管理が必要です。
スリッページと流動性の深さの関係性
スリッページは、注文時の予想価格と実際の約定価格との差を指します。AMMにおけるスリッページは、流動性プールの規模と取引量に大きく依存します。流動性が浅いプールでは、少額の取引でも大きな価格変動が発生し、スリッページが大きくなります。
例えば、10ETHと10,000USDCしかない小規模なプールで1ETHを購入しようとすると、プール内のバランスが大きく変化し、予想以上に高い価格で購入することになります。一方、1,000ETHと1,000,000USDCがある大規模なプールでは、同じ1ETHの購入でも価格への影響は最小限に抑えられます。
スリッページを管理するため、多くのDEXではスリッページ許容度を設定できます。一般的には0.5%〜1%程度に設定されることが多いですが、流動性の浅いプールや価格変動が激しい時期には、より高い許容度が必要になることもあります。スリッページ許容度を低く設定しすぎると、取引が失敗する可能性が高まります。
流動性の深さは、TVL(Total Value Locked:総ロック価値)で測られることが多く、TVLが高いプールほど安定した取引が可能です。初心者の方は、TVLが1億円以上あるプールを選ぶことで、予期しない大きなスリッページを避けることができます。また、大口取引を行う場合は、取引を複数回に分割することでスリッページを軽減する戦略も有効です。
代表的なAMMプロトコル6選の特徴と使い方
AMMプロトコルは、それぞれ独自の特徴と強みを持っています。ここでは、市場で広く利用されている6つの主要なAMMプロトコルについて、特徴や使い方を詳しく解説します。各プロトコルの選択は、取引したいトークン、利用するブロックチェーン、手数料、流動性の深さなどを考慮して行うことが重要です。
Uniswap – AMMの先駆者として市場をリード
Uniswapは2018年にローンチされた、AMMの代名詞とも言えるプロトコルです。Ethereum上で最大規模の流動性を誇り、累計取引量は1兆ドルを超えています。現在はV3が主流となっており、「集中流動性」という革新的な機能を導入しています。
Uniswap V3の集中流動性機能により、流動性提供者は特定の価格範囲に流動性を集中させることができます。例えば、ETH/USDCペアで、ETHが3,000〜4,000ドルの範囲でのみ流動性を提供するという設定が可能です。価格がこの範囲内にある限り、より高い手数料効率を実現できます。従来のV2と比較して、最大4,000倍の資本効率を達成できるとされています。
Uniswapは、Ethereum以外にもArbitrum、Optimism、Polygon、Base、BNB Chainなど複数のチェーンに展開しています。各チェーンでの取引手数料は大きく異なり、Ethereumメインネットでは10〜50ドル程度かかることもある一方、Layer2ソリューションでは1ドル以下で取引可能です。UNIトークンを保有することで、プロトコルの運営方針に関する投票に参加できます。
2024年にはUniswap V4の開発が発表され、「フック」機能により、開発者がカスタムロジックをプールに追加できるようになる予定です。これにより、より柔軟で多様な金融商品の構築が可能になると期待されています。
PancakeSwap – BNB Chainで低コスト取引を実現
PancakeSwapは、BNB Chain(旧BSC)上で最も人気のあるAMMプロトコルです。2020年9月にローンチされ、Ethereumの高いガス代問題を解決する選択肢として急速に成長しました。取引手数料は0.25%で、そのうち0.17%が流動性提供者に、0.03%がCAKEトークンの買い戻しに使用されます。
PancakeSwapの最大の魅力は、低い取引コストです。BNB Chainのガス代は通常0.1〜0.5ドル程度で、Ethereumと比較して大幅に安く取引できます。また、豊富なイールドファーミング機会があり、CAKEトークンを中心とした様々な報酬プログラムが用意されています。Syrupプールと呼ばれるステーキングプールでは、CAKEを預けることで他のトークンを獲得できます。
PancakeSwapは、ローンチパッド、NFTマーケットプレイス、予測市場、ロッタリーなど、取引以外の機能も充実しています。特にIFO(Initial Farm Offering)は、新規プロジェクトのトークンを早期に獲得できる機会として人気があります。CAKEトークンは、これらの機能へのアクセスや、手数料割引、ガバナンス投票などに使用されます。
流動性マイニングでは、特定のプールに流動性を提供することでCAKEトークンを獲得できます。APR(年間収益率)は市況により変動しますが、人気のプールでは10〜30%程度の利回りが期待できることもあります。
Curve Finance – ステーブルコイン特化型AMM
Curve Financeは、ステーブルコインや類似資産の交換に特化したAMMプロトコルです。2020年1月にローンチされ、独自のアルゴリズム「StableSwap」により、極めて低いスリッページでの取引を実現しています。
Curve Financeの特徴的なアルゴリズムは、x*y=kの定数積フォーミュラを改良したもので、価格が1:1に近い資産同士の交換に最適化されています。USDC/USDT/DAIなどのステーブルコインプールでは、100万ドル規模の取引でも0.01%以下のスリッページで実行可能です。また、ETH/stETH、WBTC/renBTCなど、ペグ資産の交換にも適しています。
CRVトークンは、Curve Financeのガバナンストークンであり、veCRV(vote-escrowed CRV)という仕組みが特徴的です。CRVトークンを最大4年間ロックすることでveCRVを獲得し、プロトコルの意思決定への投票権と、取引手数料の50%を受け取る権利を得られます。ロック期間が長いほど、より多くのveCRVを獲得できる仕組みです。
Curve Financeは、Ethereum以外にもArbitrum、Optimism、Polygon、Avalanche、Fantomなど20以上のチェーンに展開しています。TVLは40億ドルを超え、DeFiプロトコルの中でもトップクラスの規模を誇ります。多くのDeFiプロトコルがCurve Financeの流動性を活用しており、DeFiエコシステムの基盤的な役割を果たしています。
Balancer – 複数資産プールによる柔軟な運用
Balancerは、2020年3月にローンチされた、より柔軟なプール設計を可能にするAMMプロトコルです。従来のAMMが2資産の50:50プールを基本とするのに対し、Balancerは最大8種類のトークンを任意の比率で組み合わせたプールを作成できます。
Balancerの加重プール(Weighted Pool)では、例えば80% ETH / 20% DAIのような非対称な比率でプールを構成できます。この仕組みにより、インパーマネントロスを軽減しながら、特定の資産により多くのエクスポージャーを維持することが可能です。また、自動的にリバランスされるインデックスファンドとしても機能し、ポートフォリオ管理ツールとして活用されています。
Balancer V2では、プロトコルボルト(Protocol Vault)という革新的な設計を導入しました。すべてのプールの資産を単一のボルトで管理することで、ガス効率を大幅に改善し、フラッシュローンなどの高度な機能を実現しています。また、資産マネージャー機能により、未使用の流動性を他のプロトコルで運用し、追加収益を生み出すことも可能です。
BALトークンは、Balancerのガバナンストークンとして、プロトコルパラメーターの変更、新機能の実装、手数料の配分などの意思決定に使用されます。veBAL(vote-escrowed BAL)システムにより、BALと80/20 BAL/ETH LPトークンをロックすることで、投票権と追加報酬を獲得できます。
SushiSwapとRaydiumの独自機能
SushiSwapは、2020年8月にUniswapのフォークとして誕生しましたが、独自の進化を遂げています。コミュニティ主導の開発により、20以上のチェーンに展開し、多様な機能を提供しています。
SushiSwapの特徴的な機能として、xSUSHIステーキングがあります。SUSHIトークンをステーキングしてxSUSHIを獲得すると、プロトコル全体の取引手数料の0.05%を報酬として受け取れます。また、BentoBoxという資産管理レイヤーを導入し、複数のDeFi機能を効率的に利用できる環境を提供しています。Kashi(レンディング)、MISO(トークンローンチパッド)、Trident(次世代AMM)など、総合的なDeFiプラットフォームとして発展しています。
Raydiumは、Solanaブロックチェーン上の主要なAMMプロトコルです。Solanaの高速性(TPS:65,000以上)と低コスト(取引手数料:0.001ドル以下)を活かし、高頻度取引にも対応できる環境を提供しています。
Raydiumの独自性は、Serum DEXのオーダーブックと統合されている点です。流動性プールの資産がオーダーブックにも反映されるため、より深い流動性と効率的な価格発見が可能になります。また、AcceleRaytor(ローンチパッド)を通じて、新規プロジェクトのトークン配布にも参加できます。RAYトークンをステーキングすることで、追加報酬や新規トークンの割り当てを受けられます。
AMMの将来性と2025年の展望
AMMは急速に進化を続けており、2025年以降もさらなる発展が期待されています。技術革新、規制環境の整備、機関投資家の参入など、様々な要因がAMMの将来を形作っていきます。ここでは、AMMの将来性と今後の展望について詳しく解説します。
クロスチェーンAMMと流動性の統合
現在のAMMエコシステムの大きな課題の一つは、流動性の分断です。Ethereum、BNB Chain、Polygon、Solana、Avalancheなど、各ブロックチェーンに独立したAMMプロトコルが存在し、流動性が分散しています。この課題を解決するため、クロスチェーンAMMの開発が進んでいます。
クロスチェーンAMMは、複数のブロックチェーン間で流動性を共有し、シームレスな資産交換を可能にする技術です。例えば、THORChainは、ビットコイン、イーサリアム、BNB Chainなど異なるブロックチェーンのネイティブ資産を、ブリッジトークンを使わずに直接交換できる仕組みを提供しています。
流動性アグリゲーターも重要な役割を果たしています。1inch、Paraswap、Matcha(0x)などのアグリゲーターは、複数のAMMプロトコルから最適なレートを検索し、自動的に取引をルーティングします。ユーザーは一つのインターフェースから、複数のプロトコルの流動性にアクセスでき、最良の取引条件を得られます。
Layer2ソリューションの普及も、流動性の統合に貢献しています。Arbitrum、Optimism、zkSync、Polygonなどは、Ethereumの高いガス代問題を解決しながら、メインネットとの相互運用性を保っています。これにより、ユーザーは低コストで取引しながら、Ethereumエコシステムの豊富な流動性にアクセスできます。
将来的には、異なるブロックチェーン間の流動性がさらにシームレスに統合され、ユーザーはチェーンの違いを意識することなく、最適な条件で取引できるようになると期待されています。
機関投資家向けAMMソリューションの登場
これまでAMMは主に個人投資家やDeFiネイティブなユーザーに利用されてきましたが、機関投資家の参入に向けた準備も進んでいます。機関投資家がAMMを利用するためには、規制対応、リスク管理、大口取引への対応など、特別な要件を満たす必要があります。
KYC(Know Your Customer)/AML(Anti-Money Laundering)対応のプールが開発されています。Aaveが開発したAave Arcは、機関投資家向けのKYC必須のプライベートプールで、規制要件を満たしながらDeFiの利点を享受できます。同様に、Compound TreasuryやMaple Financeなども、機関向けのコンプライアンス対応ソリューションを提供しています。
プロフェッショナル向けの流動性管理ツールも充実してきています。Gamma StrategiesやArrakis Financeなどは、Uniswap V3の集中流動性を自動的に管理し、最適な価格範囲でのリバランスを行います。機関投資家は、これらのツールを使用することで、複雑な流動性管理を効率化できます。
また、プライベートAMMやダークプールの概念も登場しています。大口取引による価格影響を最小限に抑えるため、一般に公開されないプライベートな流動性プールで取引を行う仕組みです。KeeperDAOやCowSwapは、MEV(Maximum Extractable Value)対策を組み込んだ取引システムを提供し、機関投資家の大口取引をサポートしています。
保険プロトコルとの連携も進んでいます。Nexus MutualやInsurAceなどの分散型保険プロトコルは、スマートコントラクトリスクやインパーマネントロスに対する保険商品を提供しています。機関投資家は、これらの保険を活用することで、リスクを軽減しながらAMMに参加できます。
規制の明確化も機関投資家の参入を後押ししています。欧州のMiCA(Markets in Crypto-Assets)規制や、米国での規制フレームワークの整備により、機関投資家がDeFiに参加するための法的基盤が整いつつあります。2025年以降、より多くの伝統的金融機関がAMMを活用したサービスを提供することが期待されています。
まとめ
AMM(自動マーケットメイカー)は、暗号資産取引の在り方を根本的に変革した画期的な仕組みです。スマートコントラクトと流動性プールによる自動化された取引システムは、24時間365日、誰でも参加可能な金融市場を実現しました。
本記事で解説したように、AMMには従来の取引所にはない独自のメリットがあります。パーミッションレスな参加、即時決済、透明性の高い価格決定メカニズムなど、DeFiの理念を体現する特徴を持っています。一方で、インパーマネントロスやスリッページなど、特有のリスクも存在するため、十分な理解と適切なリスク管理が必要です。
Uniswap、PancakeSwap、Curve Finance、Balancerなど、各AMMプロトコルはそれぞれ異なる特徴と強みを持っています。利用目的、取引したいトークン、許容できるリスクレベルに応じて、適切なプロトコルを選択することが重要です。
初心者の方がAMMを始める際は、まず少額から始め、基本的な操作に慣れることをお勧めします。MetaMaskなどのウォレットの安全な管理、信頼できるプロトコルの選択、適切なスリッページ設定など、本記事で解説した基本事項を守ることで、安全にDeFiの世界を探索できます。
2025年以降、AMMはクロスチェーン統合、機関投資家の参入、規制環境の整備により、さらなる発展が期待されています。AMMは単なる取引ツールではなく、新しい金融システムの基盤として、私たちの資産運用の可能性を大きく広げていくでしょう。
暗号資産とDeFiの世界は日々進化しています。AMMを理解し活用することで、この革新的な金融エコシステムの恩恵を受けることができます。ただし、投資は自己責任で行い、失っても困らない範囲で参加することを忘れないでください。
注意事項
- 本記事は、情報提供のみを目的としており、投資助言や金融商品の売買を推奨するものではありません。
- 本記事では、正確な情報提供に努めておりますが、その完全性、正確性、適時性、有用性等について、保証いたしかねます。
- 本記事に記載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
- 暗号資産(仮想通貨)への投資判断は、ご自身の責任において行ってください。投資を行う際は、取引所の利用規約および取引に関する説明事項をよく読み、リスクについて十分に理解した上で、ご自身の判断と責任において行ってください。
- 本記事の内容は、予告なく変更または削除される場合があります。